和邇・和珥・丸邇・丸・ワニ氏 について。
ワニ氏
和邇氏 は、和珥・丸邇・丸 とも。
5世紀から6世紀 にかけて 奈良盆地東北部 に勢力を持った 古代日本の中央豪族です。
「和邇氏」は、2世紀頃に 日本海側から 近畿地方に進出した 太陽信仰 の朝鮮系の 鍛冶集団、または 漁労や航海術にすぐれた海人(アマ)族 とする説があります。
「和邇氏」といえば、出自に謎が多い氏族ですね。
阿田賀田須命(アタカタス)が祖とも言われていますが、その アタカタス がよくわからない存在だったりするもので。(←私にとって)
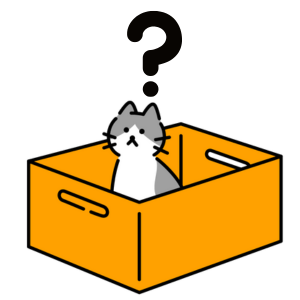
ワニ の祖
<メモ>
ワニといえば、なんだかんだで辿り着く「飯肩巣見命」も要チェック(子が 建甕槌命なんだけれども、あの 鹿島神宮祭神の武甕槌命 なのか?とか。ん?鹿?ワニどこいった?)

和珥と 和邇 と 丸 は 別物なのか?同じなのか?(結論:わかりません!)
「邇」と「珥」
「和邇」と「和珥」で 漢字の意味は違うのでしょうか?ちょっと調べてみました。↓↓↓
「邇」の意味
▼ 邇(ジ):引用(コトバンク:邇)
- 字は、
 に作り、産土神の社、生まれた地
に作り、産土神の社、生まれた地 - ちかい、ちかく、ちかづく
「![]() きを柔らげ邇(ちか)きを能(をさ)む」
きを柔らげ邇(ちか)きを能(をさ)む」
↓
「![]() きを
きを![]() (やは)らげ
(やは)らげ![]() (ちか)きを能む」
(ちか)きを能む」
![]() は、土主の上に木を植え、犬牲 を供えて祀る形で、ときには 女が ひざまずいて拝する 形を加えている例もある。
は、土主の上に木を植え、犬牲 を供えて祀る形で、ときには 女が ひざまずいて拝する 形を加えている例もある。
「邇」の読み
「邇」の、基本の読み方は「ジ」ですが、その他の読み方は以下の通りです。↓↓↓
- 名義抄:チカシ・マタ・ユヅル・ハカル
- 篇立:チカシ・ウツル・ミジカシ・トキニ・セム・ススム・マタ・ユヅル・トキ・マハルカ
「邇」の 神様
名前の「邇」のつく神様 ↓↓↓
- 宇比地邇神・須比智邇神(兄・妹)
- 邇邇芸命:古事記
- 邇芸速日命:古事記
「邇邇芸」と「瓊瓊杵」
- 天 邇岐志国 邇岐志 天津日高 日子 番能 邇邇芸命
- 天津日高 日子 番能 邇邇芸能命
- 天津日子 番能 邇邇芸命
- 日子 番能 邇邇芸命
- 天津彦 彦 火 瓊瓊杵尊
- 天津彦 国光彦 火 瓊瓊杵尊
- 天 饒石国 饒石 天津彦 火 瓊瓊杵尊
- 天 国 饒石 彦 火 瓊瓊杵尊
- 天津 彦根 火 瓊瓊杵根 尊
- 火 瓊瓊杵尊
- 天之 杵火火 置瀬尊
- 天 杵瀬命
<メモ>
・古事記:712年頃(国内向け)
・日本書記:720年頃(国外向け)
「邇芸速日」と「饒速日」
- 邇芸速日命
- 饒速日命
- 櫛玉 饒速日命
<メモ>
・古事記:712年頃(国内向け)
・日本書記:720年頃(国外向け)
・
・
ちなみに「先代旧事本紀」(成立901年~923年)では以下の通りです。↓↓↓
- 饒速日命
- 天照 国照彦 天火明 櫛玉 饒速日尊
- 天火明命
- 天照 國照彦 天火明尊
- 胆杵磯 丹杵穂 命
その他、ニギハヤヒの別名として以下があります。↓↓↓
- 神 饒速日命
- 天照御魂神
- 天照皇御魂大神
「珥」の意味
▼ 珥(ジ):引用(コトバンク:珥)
- みみだま、みみかざり
- さしはさむ、耳にさしはさむ、耳に貫く
- まるい玉、剣のつば
- ひがさ、日のかさ
 (ジ)と通じ、左耳 を切りとる
(ジ)と通じ、左耳 を切りとる (ジ)と通じ、牲を 割いて血ぬる
(ジ)と通じ、牲を 割いて血ぬる
「珥」の読み
「珥」の、基本の読み方は「ジ」ですが、その他の読み方は以下の通りです。↓↓↓
- 名義抄:サシハサム・ミミタマ
- 字鏡集:ミミタリ・ミミニアルタマ・サシハサム・カク・オホタマ
「丸」ワニ について
『日本書紀』には、ワニの表記 に「和邇」が当てられているが、より古い表記は『古事記』に見られる「丸」である。
丸には、グアン、クァンに先立つ古音として、ワン が存在した(藤堂明保:学研大漢和辞典)。当時の日本語には,「ン」という撥音は 未だ無く、n の後には、u や iをつけて二音節化する習慣があった。
・「丸」の音は wan であるが、語尾の n に i をつけて、ワニと 読み 日本語化したのである。
・「銭」の 呉音、ゼン を ゼニ と読んだのも その一例である。
・ワニ氏が 伝えていた古い記祿類には、古い用字法が残っていたのであろうが、丸(ワニ)は、和(ワ)や邇(二)に比べると、すでにその使用が廃れ始めていた。
・古事記に 登場する 稲羽の素菟 の話に 鰐が出てくるがその 鰐にしても和邇である。
・丸(ワニ)は、恐らく人名以外には使われていないとみられるほど、使用頻度は ゼロに近い。
・「和」や「邇」が文書で頻繁に使われ、ワ や 二 の音が定着したのに比べて、「丸」は、その発音が ワニ であることさえ知られなかったと言ってよい。
・更に追い打ちをかけるように、「丸」の発音は ワン から グアン に変化した。
・そうなると ワニ氏 に 丸 を当てるのを避けるようになり、代わって 和邇 を用いることが習慣化し、春日臣 に改姓されるまで、ワニ氏 は一貫して 和邇の祖、和邇臣 と表記された。
・
読み進めていると、サラッと「春日臣 に改姓されるまで、ワニ氏 …」とありますが、「ワニ氏」ここら辺が知識不足で上手く理解できずにいるんですよね。(もう少し勉強します…)
和邇氏メモ
以下、「和邇氏についての情報」メモ。
- 小野家から和邇家が出る
- 登美家第八代当主「阿田賀田須(アタカタス)」の分家が和邇家の始まり(①)
- 6代孝安大王(国押人)の兄「天足彦国押人命」が和邇の祖(②)
- ①と②は矛盾?
参考サイト

ワニ氏|まとめ
以上、
「和邇氏」についてのブログ記事でした。


