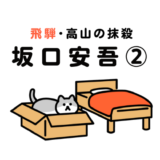坂口安吾 の 新日本地理「飛騨・高山の抹殺」について。(その ③)
- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?
- ② 古い交通路は海ではなく山だった?
- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪
- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ
- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!
- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性
- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ
- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!
- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!
- ⑩ 身内のケンカと日本神話
- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事
- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨
- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄
- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田
- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ
- ⑯ 死をまぬがれる聖泉
- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺
- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠
・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧
※ 当記事は、上記シリーズ「③」です
安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ③
「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺」というお話は、「青空文庫」で、読むことが出来ます。
\ 全文はこちら /
が、私がこれらを記事にする目的は「誰かや何かへ対する批判」ではありません。
複数の立場から書かれた異なる伝承(「記紀」含む)の内容から「そうした言葉が残された背景を知りたい」という思いがメインです。
その点を、ご理解の上、読んでいただけると有難いです。
(堅苦しくなりましたが、要は「和やかにいこうね」っておねがいです)
「白黒の文字」だけだと、情報が上手く入らない「ポンコツ脳」なので、自分の為にちょっと整理してみました。↓↓↓
飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪
・青空文庫編:安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺――中部の巻――坂口安吾
↑↑↑ 上記の内容に「改行」「空白」「…」「リンク」「補足」「画像」等 をプラスさせていただきました ↓↓↓

赤:飛騨国・緑:東山道(引用:Wikipedia)
※ 「斜体」が「坂口安吾」の文章です。↓↓↓
ヒダ の一の宮を 水無神社 という。
祭神は 以下の15柱で、水無大神 と総称される
<主祭神>
・御歳大神:「水無神」と呼ばれる
<配神>
・大己貴命
・三穗津姫命
・応神天皇
・高降姫命 ※1
・神武天皇
・須沼比命 ※2
・天火明命
・少彦名命
・高照光姫命
・天熊人命
・天照皇大神
・豊受姫大神
・大歳神
・大八椅命
※1 高降姫命:『先代旧事本紀』地祇本紀では、大国主神は、辺都宮の高降姫神(高津姫神)と婚して事代主神を生んだとしている。これを胸形三女神の多岐都比売と解し、神屋楯比売をその別名かと疑う説もある。
※2 須沼比神:大年神が娶った「伊怒姫」の親神(=神活須毘神?)

(水無神社 は)一の宮だが 現社格は近代まで 県社ぐらいの低いものだったらしく、祭神 が今もハッキリとしない。
神武天皇 と云い、大国主 と云い、その他色々で、水の神サマ であるか 風の神サマ であるか、それもハッキリはしていない。
・
・
ヒダの伝説 によると、
「神武天皇 へ位をさずくべき神 が この山の主で、身体が一ツで 顔が二ツ、手足四ツ の 両面四手 という人が 位山の主 である。

両面宿儺
(引用:Wikipedia)
彼は 雲の波 をわけ、天ツ舟にのって この山に来て 神武天皇 に位をさずけた。
そこで 位山 とよび、船のついた山を 船山 という」
これはヒダの国守であった 姉小路基綱 の ヒダ八所和歌集 裏書きの意訳ですが、これがだいたい ヒダの伝説の筋です。
・
・
現に 水無神社 のすぐ近く に 位山 と 船山 とあり、山上には 巨石群、古墳群 があるそうです。
が、しかし 前文の作者 は、
「位山 は 諸木の中 でも 笏に用いる 一位木 が多い。
麓をまわれば 二十余里、宮殿(水無神宮の由)の奥、また府(現高山市)から麓まで 七里余」
…とある。
位山 と 船山 は 高山 や 水無神社 から頂上まで でも 一里半 か 二里ぐらい。
里数が違う。
<メモ>
・一里:約 4キロメートル
・
・
そこで、位山 は 乗鞍 だというのが 郷土史家 の 定説 である。
むかしは 乗鞍 を 位山 と云った。
 乗鞍岳は淡山(アワヤマ)だった?|天と地のはじまり
乗鞍岳は淡山(アワヤマ)だった?|天と地のはじまり
位山 が 乗鞍 を指すのであると 多くの史料に見られる 位山 の記事にピッタリする。
その代り、こまったことには 船山 がない。
\ ??? /
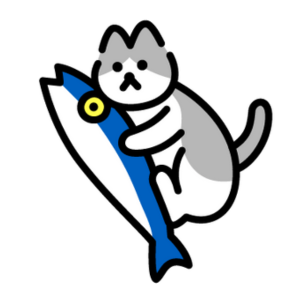
水無神社の歴史 という本には、八所和歌集の記事からだと 乗鞍 にも当るし現在の 位山 にも当ると云っている。
しかし乗鞍の麓 には 船山 はないが 船津 がある。
今は 神岡町 であるが、昔から有名な船つき場で、今の町名の 神岡 が古い名かどうか知らぬが、船津 が同時に 神岡 なら、これを 船山 と解して悪くもなかろう。
神通川 をさかのぼって 船津 で船をのりすてて 乗鞍 へ登った。
天ツ船 は 神話では 山上へ到着 するが、神通川 をさかのぼって 舟行の限界点 として適当な 船津 でのりすてた。
そう俗に、現実的に解して悪くはないであろう。
<メモ>
・坂口安吾は 1906年(明治39年)生~1955年(昭和30年)没
・荒城郡 → 吉城郡 → 神岡町 1950年(昭和25年)発足(吉城郡 船津町、阿曽布村、袖川村 が合併)
・
・

船津の隣り字は 石神 だの 阿曾布 だのと この氏族 にふさわしい 古い地名 が多い。
このあたりは昔は スワ と云い、今に古 スワ の地名がある由。
舟をすてた最初の聚落 が スワ で、乗鞍 を越えた 信濃側 にもスワがある。
↑↑↑
<メモ>
「船津」周辺に「スワの 地名」を(ネット上から)見つけることは出来ていないが「大津神社」(諏訪系の神社:江戸時代までは諏訪大明神と称していた)は あった。↓↓↓
【大津神社】住所:岐阜県 飛騨市 神岡町 大字船津
・玄松子の記憶:大津神社(紋:立梶の葉)
・その他 全国の「大津神社」はこちら → ★
<補足>
愛知県側の岐阜県に「諏訪山」「諏訪町」など スワの地名 が見えるが、この文章で言っている場所はここのことではないと思われる。(文章中の場所は「乗鞍岳 の 岐阜側麓」なので違う)
<余談>
持統天皇に謀反の疑いをかけられて死に至ったのは「大津皇子」だったっけ。
※ ↑↑↑「斜体」が「坂口安吾」の文章です。
関連場所の地図
参考サイト
安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ③|まとめ
- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?
- ② 古い交通路は海ではなく山だった?
- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪
- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ
- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!
- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性
- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ
- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!
- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!
- ⑩ 身内のケンカと日本神話
- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事
- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨
- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄
- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田
- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ
- ⑯ 死をまぬがれる聖泉
- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺
- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠
・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧
※ 当記事は、上記シリーズ「③」です
以上、
「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ③」についてのブログ記事でした。