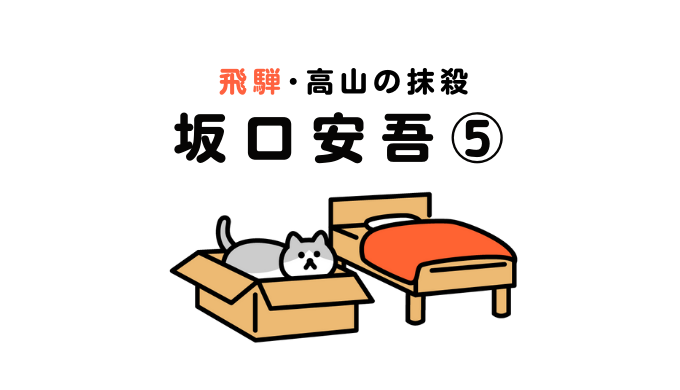坂口安吾 の 新日本地理「飛騨・高山の抹殺」について。(その ⑤)
- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?
- ② 古い交通路は海ではなく山だった?
- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪
- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ
- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!
- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性
- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ
- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!
- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!
- ⑩ 身内のケンカと日本神話
- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事
- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨
- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄
- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田
- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ
- ⑯ 死をまぬがれる聖泉
- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺
- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠
・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧
※ 当記事は、上記シリーズ「⑤」です
安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑤
「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺」というお話は、「青空文庫」で、読むことが出来ます。
\ 全文はこちら /
が、私がこれらを記事にする目的は「誰かや何かへ対する批判」ではありません。
複数の立場から書かれた異なる伝承(「記紀」含む)の内容から「そうした言葉が残された背景を知りたい」という思いがメインです。
その点を、ご理解の上、読んでいただけると有難いです。
(堅苦しくなりましたが、要は「和やかにいこうね」っておねがいです)
「白黒の文字」だけだと、情報が上手く入らない「ポンコツ脳」なので、自分の為にちょっと整理してみました。↓↓↓
両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!
・青空文庫編:安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺――中部の巻――坂口安吾
↑↑↑ 上記の内容に「改行」「空白」「…」「リンク」「補足」「画像」等 をプラスさせていただきました ↓↓↓

赤:飛騨国・緑:東山道(引用:Wikipedia)
※ 「斜体」が「坂口安吾」の文章です。↓↓↓
さて、船で ヒダ へ来て 神武天皇 に位をさずけた 位山 の 主 のことを 姉小路基綱 の 八所和歌集は 一体にして顔が二ツ、手足四本、これによって 両面四手 と云う、という、
この 怪人物は 日本書紀にチョッピリと記事があって、仁徳天皇65年の条に、
「ヒダの国に 宿儺(スクナ。以後カナで書きます)という者があって、躰は一ツ、顔が二ツたがいに後向きについてる。
各々の顔に 各々の手足がある。
力強く、早業で、左右に剣をさし、四ツの手で二ツの弓を同時に使う。
皇命にしたがわず、人民をさらッて楽しみとするので、難波根子武振熊 をつかわして殺させた」 とある。
- 和珥武振熊
- 難波根子武振熊(日本書紀)
- 難波根子建振熊(古事記)
- 和珥氏の祖
- 神功皇后摂政時 における 忍熊皇子の反乱 の際、討伐に遣わされた人物
難波根子武振熊…って名前しか知らないなぁ…と思って、軽く調べて見たら 別名「和珥武振熊」ですと。
あぁ…出た!ワニ… 理解が難しい一族。
和珥・和邇・丸…が全部同じモノを指すのか?さえ、よくわからない。
というわけで、ちょっと 横道に逸れますが…
「ワニ」について 復習してみたりしつつ… ↓↓↓
\ 「ワニ」について /
 和邇・和珥・丸邇・丸・ワニ氏 について
和邇・和珥・丸邇・丸・ワニ氏 について
「ワニ」については、復習してもわからない事が多いので、ひとまず 坂口安吾 の 本文に戻ります ↓↓↓
・
・
ただ、これだけの記事があるにすぎません。
もっとも、そのほかに彼の異形のサマを説明して、顔が二ツだが、頂イタダキ合いて頸ウナジなし、つまり二ツの顔の後頭部はピッタリとくッついて一ツになってるという意味らしい。
また、膝ありて膕踵なし、ヨボロクボ は クビス(踵:カカト)の由ですが、この文章からは様相の見当がつきません。
ヒダ ではこの 怪人物を 両面スクナ と云っています。
書紀では クマソ か 酒顛童子 のような悪漢として カンタンに殺されてますが、ヒダ ではこれが 天の船で位山へついた という 日本の 主 で、
大和 の 敵軍 が 攻めてきたとき、ひそんでいた 日面の出羽の平 の ホラアナ をでてミノの 武儀郡 下ノ保 で戦い敗れて 逃げ戻り、宮村で殺された。
その 死んだ地 が ヒダ一の宮の 水無神社 であるという。
<疑問>
ん…?「日本の主」と「大和の敵軍」とあるが、「日本」と「大和」は 別物 ということ…?

「???」…と、思っていたら、以下のサイトにわかり易く解説が書いてありました。↓↓↓
「天武天皇 も 持統天皇 もヒダ 王朝出身 の 皇統 に相違ないのですが、嫡流 を亡ぼして、故郷のヒダを敵にしたから…」と。
嫡流 と 庶流 の違いなんだ…と。(たぶん)
確かに「天皇の和風諡号」を見てみると、「日本」と「倭(=大和?)」の2パターンが見受けられますね。
・
・
スクナ がひそんでいた 出羽ノ平のホラアナ は今もあって スクナ様のホラアナ と怖れられて、そこへ誰かが登ると 村に祟りがある と信じられております。
私はそのホラアナ(鍾乳洞ですが)へもぐりこんできました。
スクナ様の 祟りかも知れませんが、ヒドイ目に会いました。
残念ながらまったく半死半生 でしたよ。
そこは 高山 から 平湯、乗鞍 の方へ 五里ぐらい行った 丹生川村 の 日面 というところで
自動車を降り、スクネ橋を渡って 道の幅一尺 か 二尺ぐらいの キコリ径を 谷ぞいに 山にわけいる。
歩くこと十五分か二十分ぐらい。
そこからキコリ径をすてて 径のない山腹をよじ登る。
この悪戦苦闘、余人は知らず、拙者ならびに 同行の大人物は 一時間ですよ。
長い間ふりつづいた梅雨が やんだばかり。
特に前日は 大豪雨で ヒダの谷川は出水があった。
その翌日だ。
両手に すがるべき木の根が みつかると安心ですが、手にさわるものは 概ね朽ち木で、つかまると折れたり抜けてきたりで、確実な木の根や枝を見出すのが大変だ。
足場にかけた岩まで長雨で地盤がゆるみ 土もろともグラグラ ぬけだす危なさ。

案内人が 方向をまちがえなかったので助かったのですが、さもないと疲労にくたばって谷へ落ちたに相違ない。
途中ロッククライミングが二ヶ所。
ここだけ 針ガネ をたらしてありました。
しかし ブラブラ たれてる 針ガネだから 握ってもすべるし、岩もぬれてすべる。
手も足もかけ場に窮して、一息でも 気力を失うと 墜死するところでした。
こんな難路とは知りませんから、豪雨の直後という悪条件を考慮に入れる要心も怠り、特別な用意が一切ないから、服は泥だらけ。
それまでの 調査のメモ をコクメイにつけておいたノートを 四ン這いの 悪戦苦闘中にポケットから 落して紛失しました。
しかし イノチを落さないのが 拾い物さ。
こッちは 商売だから我慢もできるが、同行の 大人物には 気の毒千万で、彼は 翌朝の目覚めに寝床から這い起ることができないのです。
必死に 手足に力をこめても、二三分間は一センチも上躰が持ちあがらないのですよ。
私のことは 言わぬことにしましょう。
この記述の方法を 日本古代史の 要領と云うのです。
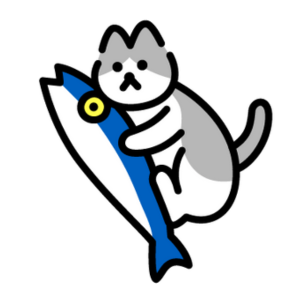
この難路を どうして予知しなかったかというと、
里の人は スクナ様のタタリを怖れて登らぬ し、
里人への遠慮か それは ヒダの全部の人々にもほぼ共通して、相当の土地の 物知りも 登っておらず、
昔の記録に 日面 の出羽ノ平の ホラアナとあるから、谷川をさかのぼると 出羽ノ平という平地があって ホラアナがあるのだろうと考えている。
これが大マチガイで、谷川を一足はいってからは 平地が全くなく、鍾乳洞 まで登りつめても 全然平地はありません。
しかし、この山頂の 尾根づたいの 山上に 平地があるらしい。
正しい地図を見ると、そうらしいのです。
その山上の平地が 出羽ノ平かも知れません。

鍾乳洞は いつの時代か 人々が斧で穴をひろげた跡が 歴然たるものです。
十間も行くと 四ン這いになるところがあるが、そこをくぐって 廊下のようなところを 這い登ると だんだん広くなって、相当の大広間になり、その マン中あたりに ナワのような太さの 水流が落ちているところがあって、自然に 石像のように 変形した 濡れ石ができていた。
その広間も 人工でひろげたものです。
水気は わりに少く、天井の石を くずしてひろげたから ツララもなく、水のたれるところに 大きくても 一寸四方ぐらいの カブトのようなのが出来てるだけです。
相当の 人数が ひそみ隠れていられるでしょう。
※ ↑↑↑「斜体」が「坂口安吾」の文章です。
関連場所の地図
参考サイト
安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ④|まとめ
- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?
- ② 古い交通路は海ではなく山だった?
- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪
- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ
- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!
- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性
- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ
- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!
- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!
- ⑩ 身内のケンカと日本神話
- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事
- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨
- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄
- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田
- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ
- ⑯ 死をまぬがれる聖泉
- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺
- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠
・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧
※ 当記事は、上記シリーズ「⑤」です
以上、
「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑤」についてのブログ記事でした。