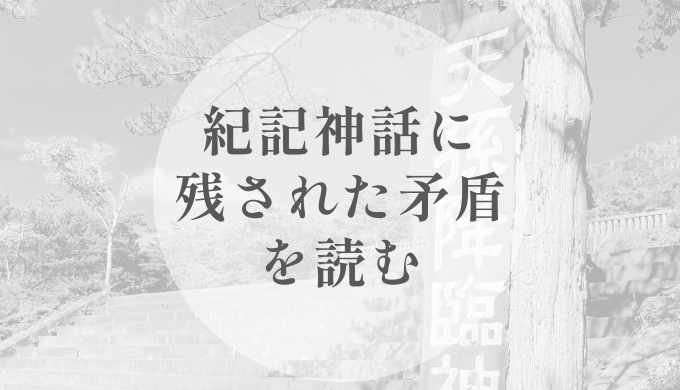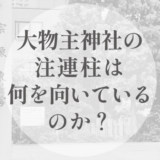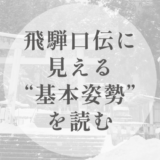『古事記』や『日本書紀』を読んでいると、どうしても引っかかる部分があります。
同じ出来事なのに語り方が違う、系譜が合わない、説明が途中で途切れる…。
それらは本当に「矛盾」なのでしょうか。
この記事では、記紀に残された違和感を手がかりに、何が書かれ、何が書かれなかったのか。
その設計を読むことを試みます。
目次
「矛盾」は、悪意やミスとして読むしかないのか

『古事記』や『日本書紀』を読み進める中で、読者が最初に抱く違和感は、「なぜ、こんな食い違いが残っているのか」という点かもしれません。
同じ出来事が別の形で語られ、系譜が一致せず、説明が途中で止まってしまう。
その様子を前にすると、「書き手に何か意図があったのではないか」と感じるのは、自然な反応です。
ときにそれは、「悪意ではないか」という疑念として立ち上がります。
一方で、あまりにも複雑な構成や 情報量を見れば、「単なる編集ミスだったのでは」と考えたくなる場面もあります。
けれど、本当にそれだけでしょうか。
記紀は、複数の立場や記憶、相反する系譜をまとめ上げた、極めて特殊な文書です。
そこに残された「矛盾」を、悪意かミスかの二択で処理してしまうと、かえって見えなくなるものがあるように思えるのです。
同じ出来事が、なぜ複数の形で語られているのか

記紀を読んでいると、同じ出来事が、少しずつ異なる形で語られている場面に何度も出会います。
登場人物の系譜が違う、立場が入れ替わる、評価が変わる…。
たとえば、スサノオ命の扱いは、その典型ではないでしょうか。
天上では乱暴者として追放され、地上では八岐大蛇を退治する英雄として語られる。
さらに系譜や役割も文献ごとに揺れ動き、一貫した像を結びません。
ひとりの神に、相反する評価が重ねられていること自体が、記紀の語りの特徴をよく示しています。
また、出雲系の神々と天孫系の神々の関係においても、対立・服属・婚姻・調停といった異なる構図が重ねて語られています。
どれか一つに整理されることなく、複数の見方が併存している点も、同じ構造と言えるでしょう。
これを「どちらが正しいのか」という視点で読もうとすると、どうしても混乱が生じます。
けれど、そもそも記紀は、ひとつの立場から書かれた物語ではありません。
異なる地域、異なる氏族、異なる記憶 が持ち寄られ、それらを一つの文書としてまとめ上げる必要があったのです。
そう考えると、語りが一つに統一されていないこと自体が、不自然とは言い切れなくなります。
複数の語りが並置されているのは、「決められなかった」のではなく、「決めなかった」結果なのかもしれません。
記紀が抱え込んだ、消せなかった記憶

もし記紀が、勝者だけの記録であったなら。
不都合な系譜や、対立の記憶は、もっと徹底的に消されていたはずです。
記紀では、ある系譜が正統として語られる一方で、また それと並行する別系統の存在が、完全には否定されずに残されています。
たとえば、ニギハヤヒ命 の存在が、その一例でしょう。
天孫降臨とは別の系譜を持ちながら、敵として完全に排除されることもなく、むしろ正統な血筋として扱われる側面も残されています。
一つの系譜に統合しきれない記憶が、否定されない形で併存しているように見えます。
勝者の記録であれば消されていたはずの痕跡が、あえて曖昧な形で抱え込まれているようにも見えます。
たとえば、天孫系の系譜が中心に据えられながらも、在地勢力や別系統の神々が完全には排除されず、物語の周縁や別伝として残されている点も、その一つです。
それでもなお、食い違いや重複、説明の曖昧さが残っている。
それは、完全に消すことができなかった記憶が、確かに存在していたことを示しています。
それぞれの語りには、それぞれの「正しさ」があり、どれか一つを切り捨てることは、新たな対立を生む危険を孕んでいた。
だからこそ、記紀は矛盾を抱え込んだまま成立した。
その不安定さは、弱さではなく、調停の痕跡として読むこともできるのです。
これ以上、血を流さないための「編集」

記紀が編まれた時代、過去の出来事をそのまま「実録」として書くことは、極めて危険な行為だったはずです。
どの系譜が正統なのか、誰が正しいのかを断定すれば、それは新たな争いの火種になりかねません。
そこで選ばれたのが、「神話」という形式でした。
出来事を直接語らず、象徴や物語へと変換することで、衝突を避けながら、記憶だけは残す。
矛盾や曖昧さは、書き損じではなく、これ以上血を流さないための “安全装置“ として編集された可能性があります。
はっきり言い切らない。
一つに決めない。
それでも、完全には消さない。
その編集方針が、記紀の構造そのものに刻まれているように思えるのです。
書かれなかったことが、今も沈黙している理由

記紀には、多くのことが書かれています。
けれど同時に、語られていないこと、途中で止められた話も数多く存在します。
それらは、単なる欠落ではありません。
書かなかったこと、書けなかったこともまた、設計の一部だったと考えることができます。
すべてを言葉にしないことで、読む人が決めつけずに済む余白が生まれる。
その沈黙は、今も私たちに問いを投げかけ続けています。
記紀に残された矛盾とは、過去をめぐる争いを終わらせるため に選ばれた、ぎりぎりの表現 だったのかもしれません。