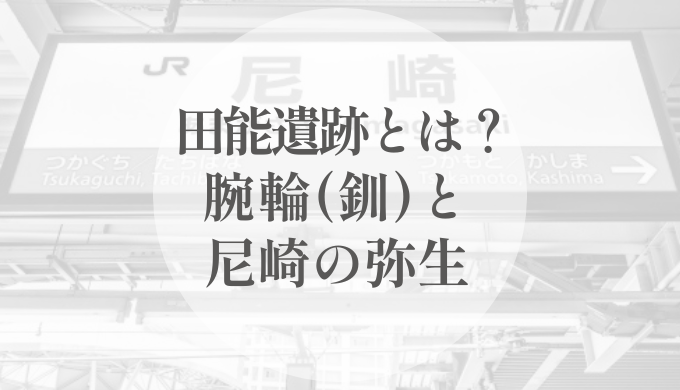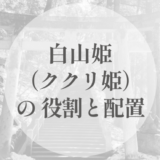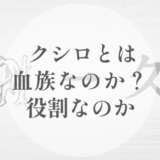尼崎(兵庫県)に、弥生時代の遺跡があると聞いて、すぐに具体的なイメージが浮かぶ人は多くないかもしれません。
けれど、田能遺跡から出土した白銅製の釧(腕輪)や大量の管玉を前にすると、少し立ち止まりたくなります。
それらは「飾り」や「権力の象徴」という言葉だけでは、どうにも説明しきれない姿をしているからです。
この記事では、神話や系譜に入る前に、実際に身体に着けられていたものから、尼崎の弥生が何を残そうとしたのかを読み始めてみます。
※なお、田能遺跡から出土した「釧(腕輪)」については、 装飾品では説明しきれない違和感を起点に、以下の記事で詳しく掘り下げています。↓↓↓
[関連記事:釧は「装飾品」だったのか|身体に着け続けられた理由を読む]
目次
尼崎に、なぜ弥生の「腕輪」が残っているのか

尼崎には、「田能遺跡」という弥生時代の遺跡があります。
そう聞いても、多くの人は少し意外に感じるかもしれません。
私自身もそうでした。
育った土地でありながら、尼崎を「古代の気配が濃い場所」として意識したことは、正直ほとんどなかったからです。

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した釧)
けれど、田能遺跡から「釧(腕輪)」が出土している、という事実に触れたとき、引っかかりが生まれました。
それは、武器でも農具でもなく、ましてや土器でもない。「身体に着けるもの」が、この土地から出ている、という点です。
 ぽの
ぽの
尼崎は、古代の王都でも、神話の中心地でもありません。
むしろ、山と海のあいだ、川の流れが集まり、通過と滞留が交差する場所です。
そうした土地において、「腕に着けるもの」が残されていること自体が、何かを語り始めているように思えました。
それは装飾だったのか、役割だったのか。
この段階では、まだ答えは出ません。
ただ、「なぜ尼崎で、なぜ腕輪なのか」という問いだけが、先に残りました。
田能遺跡という場所が、あまり語られてこなかった理由
田能遺跡は、教科書的な意味での「有名遺跡」ではありません。
大きな王墓があるわけでもなく、明確な首長像が浮かび上がるわけでもない。
だからこそ、歴史の物語としては語りにくかったのだと思います。
けれど、「語りにくさ=重要でない」ではないはずです。
むしろ、中心から少し外れた場所、制度化される前の層が残りやすい場所だった可能性もあります。
尼崎という土地は、古代から「通過点」「境界」「間」に置かれやすい位置にありました。
山でも海でもなく、どちらにも接続している。
その曖昧さが、強い物語を持たない代わりに、痕跡を残した…そんな配置も考えられます。
田能遺跡が静かに扱われてきた理由そのものが、すでに一つのヒントなのかもしれません。
白銅製の釧と、大量の管玉という違和感

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した管玉)
さらに気になったのが、管玉の存在です。
正直に言うと、最初に知ったときは、私もごく素直に「首飾り」だと思っていました。
男性の胸元から出土した、と聞けば、「豪華な装身具を身につけた人物像」が、まず頭に浮かびます。
 ぽの
ぽの
けれど、少しずつ違和感が出てきました。
尼崎は水害も多く、いわゆる中心的な場所ではありません。
大人になった今は、「大王が住む場所」や「葬られる場所」とは、少し結び付きにくい土地だと感じています。
その上で、あらためて資料を読み直していくと、管玉の数が多く、しかも大きさや長さにばらつきがある。
首飾りとして完成された姿を想像しようとすると、どこか噛み合わないのです。
副葬品として見ても、配置はどこか曖昧で、「飾って埋めた」というより、何かの途中段階にあったもの、あるいは繰り返し使われてきた痕跡のようにも見えてきます。
装飾品として考えること自体が間違いだ、と言うつもりはありません。
ただ、それだけでは説明しきれない何かが、ここには残っている。
そう感じ始めたところから、管玉の見え方が少しずつ変わっていきました。
装飾品では説明できない「身体に着け続ける」という選択

装飾品として考えていた頃は、腕輪についても、あまり深く考えたことがありませんでした。
先にも書いた通り、「古代の人もオシャレだったんだな」くらいの感覚です。
金属でできていて、形も整っている。
それだけ見れば、権力や身分を示す装身具だと思うのが自然でした。
けれど、釧について調べ始めてから、少しずつ引っかかりが増えていきます。
まず、「腕に着ける」こと自体が前提になっている点です。
首飾りや耳飾りと違って、釧は簡単に着脱する形をしていないものが多い。
一時的に身につける装飾品というより、日常的に、あるいは長い時間、身体と一体化していたようにも見えます。
さらに、戦うための装備として考えると、どうにも向いていません。
動きを妨げる可能性があり、実用性も高くない。
それでも、あえて腕に着け続けるという選択がされている。
この時点で、「オシャレ」や「誇示」だけでは説明が足りないと感じ始めました。
釧は、見せるためのものというより、着け続けること自体に意味があったのではないか。
そう考えるようになってから、腕輪の見え方も、少しずつ変わっていきました。
この「着け続ける」という違和感は、田能遺跡だけに限った話ではありません。
同じ腕輪(釧)でも、別の遺跡では、さらに踏み込んだ状態で見えてくるものがあります。↓↓↓
[関連記事:釧は「装飾品」だったのか|身体に着け続けられた理由を読む]
釧(クシロ)は、何を問いとして残したのか

ここまで見てきて、釧について「分かった」と言えることは、実はそれほど多くありません。
腕に着けるものだったこと。
装飾品としてだけでは説明しきれないこと。
そして、身体に着け続けるという前提が、どこか特別に見えること。
それらは確かに感じ取れるのですが、「だから釧とは何なのか」と問われると、言葉に詰まります。
正直に言えば、少し前までの私は、そこまで考えようともしていませんでした。
腕輪は腕輪。
古代の人の装身具。
それ以上でも、それ以下でもない。
そう受け取ってしまえば、それで話は終わってしまうからです。
けれど、管玉と並んで出土していることや、貝の腕輪を思わせる形が金属で再現されていることを知るにつれ、「なぜ、わざわざ?」という問いが残るようになりました。
素材ではなく、形や役割が引き継がれているように見える。
その違和感は、簡単に消えてくれません。
釧は、特定の神の名として大きく語られることもありません。
氏族名として前面に出てくるわけでもない。
けれど、確かに“存在していた”痕跡だけは、こうして残っています。
もしかすると釧は、「何かを説明するための存在」ではなかったのかもしれません。
守るものだったのか。
引き受けるものだったのか。
あるいは、そのどちらでもあったのか。
この時点では、どれも断定できません。
ただ、釧が残しているのは答えではなく、「問いそのもの」なのだと感じています。
なぜ、身体に着ける必要があったのか。
なぜ、神名として語られなかったのか。
なぜ、制度や言葉にまとめられず、痕跡だけが残ったのか。
この連載では、いきなり答えを出すつもりはありません。
まずは、その問いが生まれた場所に、少し立ち止まってみたいと思います。