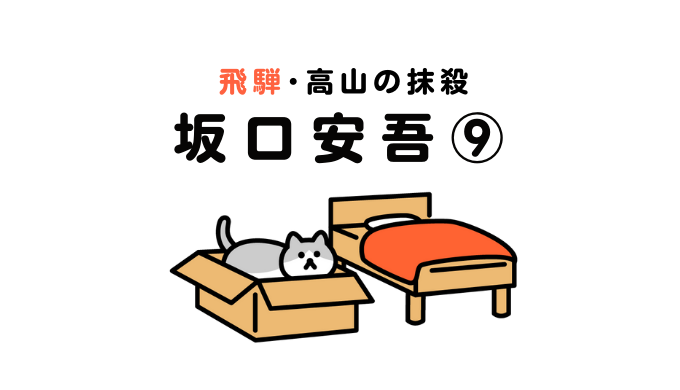坂口安吾 の 新日本地理「飛騨・高山の抹殺」について。(その ⑨)
- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?
- ② 古い交通路は海ではなく山だった?
- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪
- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ
- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!
- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性
- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ
- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!
- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!
- ⑩ 身内のケンカと日本神話
- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事
- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨
- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄
- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田
- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ
- ⑯ 死をまぬがれる聖泉
- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺
- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠
・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧
※ 当記事は、上記シリーズ「⑨」です
安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑨
「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺」というお話は、「青空文庫」で、読むことが出来ます。
\ 全文はこちら /
が、私がこれらを記事にする目的は「誰かや何かへ対する批判」ではありません。
複数の立場から書かれた異なる伝承(「記紀」含む)の内容から「そうした言葉が残された背景を知りたい」という思いがメインです。
その点を、ご理解の上、読んでいただけると有難いです。
(堅苦しくなりましたが、要は「和やかにいこうね」っておねがいです)
「白黒の文字」だけだと、情報が上手く入らない「ポンコツ脳」なので、自分の為にちょっと整理してみました。↓↓↓
美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!
・青空文庫編:安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺――中部の巻――坂口安吾
↑↑↑ 上記の内容に「改行」「空白」「…」「リンク」「補足」「画像」等 をプラスさせていただきました ↓↓↓

赤:飛騨国・緑:東山道(引用:Wikipedia)
※ 「斜体」が「坂口安吾」の文章です。↓↓↓
つまり日本の官撰史は 諸国へ ありがたそうな神様 や 恐しそうな悪者 を分散させて その土地のユカリのものとし、また土地の 豪族やその歴史をとりいれて 自分の身内の神 としました。
しかし、先にも申したように 神様を 諸国へ分散させたと云っても、その神様は 実はごく少数しか原形がなくて、諸国の 各時代へ 分散した 多くのものが 実はその少数の 原形の変形 であり、くりかえし にすぎない。
そのなかで、ありがたそうな神様 の分配には一切あずからなくて、両面スクナ という奇怪な悪漢だけ分配されてるのが ヒダの国 です。
ところが ヒダの伝説 は 書紀とアベコベのこと を伝えており、偶然にも 国史と伝説まで がスクナを両面的に 仕立てる結果になりましたが、実は スクナが両面 でなければならぬ本当の理由 はこれで、これによって 本質的に 両面でなければならぬのが スクナである。
そう見ても 差支えはないようです。

つまり スクナの両面 の 片面は ヒダ側の伝説 となって伝われるのみで、ヒダの国史に はスクナの反対の分身、ありがたい方の分身の分配が全然ないし、他の ありがたそうな神様も 全然分配されておりません。
古代史に於ては珍しい例で、全然というのは面白い。
つまり、分配されない理由 があって、それをヒダ側の 伝説が 補足説明していると見ることができますまいか。
よその国には タカマガ原 だの、天の岩戸 だのと、方々に見られますが、ヒダには 国史に ツジツマを合せようとしたような跡は ミジンもありません。
よその国は 国史の指示に よって、また 人たる者の 自然の気風 によって、国史にツジツマを合せた。
しかし ヒダの国 はツジツマを合せる必要はない。
ヒダ に ツジツマを合せたのが 国史の方 なのだ。
ヒダの方からツジツマを合せる理由はない。
だから 全然ツジツマは 合わないけれども、国史が ツジツマを合せた原形たるものは 何の手入れも施されず、したがって 雑然としながらも なにがなし厳たる貫禄をもって、みんな ヒダに実在 しているようです。
古代の国史の 地名の原形 らしいものは 殆ど全部 この地 で見ることができます。

天孫降臨 の段に、天稚彦 を 葦原の中ツ国 につかわした。ところが 日本平定の大事 を忘れて 大国主の娘と良い仲になって八年たっても帰らない。
そこで使いの鳥を 偵察にやったら ワカヒコ は鳥を射殺してしまった。
その矢が タカマガ原 の大神のところへ飛んできたから手にとって見ると血がついてる。
それを下界へ投げ返したら ワカヒコ の胸に突き刺さって死んだという。
これも両面伝説の一ツで、五瀬命 や 忍熊王 や スクナ と同じく 矢で死んでいる。
殺した方は 天皇側 で、自分の肉親 の 大神 であることは、古事記 の 日本武尊 が 天皇に殺されたのと同じい。
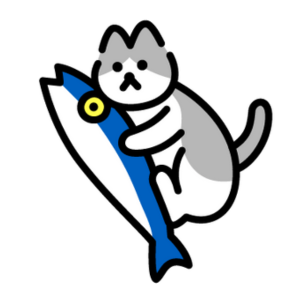
天ノワカヒコとは 兄弟ではないが、アジスキ高根彦 という親友がいて、友の死をとぶらいに来た。
ところが顔が ワカヒコとそッくりだから、アッ生きていると云って 遺族がすがりついた。
すると アジスキは オレを死者扱いは何事であるかと 刀をぬいて 喪屋を切りふせ足で蹴って突き離した。
美濃国の 藍見河の河上 の 喪山 がそれだと云う。
<メモ>
・藻山神社(岐阜県 美濃市 大矢田)
つまりワカヒコの喪屋は切りふせて蹴とばされて離れ去っている。
 伝承の地が沢山!美濃の大矢田|ワカヒコの喪屋・スサノオの大蛇…など
伝承の地が沢山!美濃の大矢田|ワカヒコの喪屋・スサノオの大蛇…など
これは 日本式尊 の 白鳥伝説 と カラの墓 にも似ているし、五瀬命 や スクナ が矢で殺されて後、死所や 墓所がハッキリせず、伝わる死所と 墓所の位置とが離れているのにも似ている。
そして、美濃の藍見川のほとりとあるが、伝説上の スクナの負傷地 もこのあたり であるし、日本武の負傷の場所 も、それから、ミノ、ヒダ をめぐって 天武持統朝 に妙なことが行われた のも、みなこの近辺をさしているのである。

そして 国史の 不破の関 は ここではない が、人麻呂 が歌によむ 不破山 は実はこのあたりにあって、恐らく 喪山近辺の山の 一ツ か 総称 か であり、
したがって 不破山 を越えて行った筈の ワサミガ原 の かり宮 というのも 不破の関 ではない筈 である。
<メモ>
・ワサミガ原?=波佐見?=?
地名をさがせば、多くの原形はたいがいそろっておる。
ミノ、ヒダ に ない原形はない ほどです。
そして、天ノワカヒコ を 葦原の中ツ国 につかわした。
その 日本のマンナカ の 大国主の住む という 中ツ国 が ミノの 藍見川 のホトリ であるという。
【藍見川=長良川】
<メモ>
・藍見川=長良川
しかし、これぐらいのことに驚くことは毛頭ない。
もっと、もっと、重大なことはいくらもある。
大和朝廷の方がいかに多く ヒダ、ミノ の地名をかりて 自分の土地を コジツケたか。
それを証明する例はあとで申上げます。
※ ↑↑↑「斜体」が「坂口安吾」の文章です。
関連場所の地図
参考サイト
安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑨|まとめ
- ① 飛騨には重要な古代史記事がない?
- ② 古い交通路は海ではなく山だった?
- ③ 飛騨の諏訪 と 信濃の諏訪
- ④ 山を越えて飛騨から穂高(信濃)へ
- ⑤ 両面宿儺は日本の主であり大和の敵?!
- ⑥ 両面宿儺とヤマトタケルの類似性
- ⑦ 日本神話は「二面性の暗示」だらけ
- ⑧ 重大な史実は各地へコピペ分散?!
- ⑨ 美濃(岐阜)は古代地名原形の宝庫?!
- ⑩ 身内のケンカと日本神話
- ⑪ 元明天皇が行った妙テコリンな事
- ⑫ 壬申の乱に出てこない飛騨
- ⑬ 敗者の大友皇子と蘇我赤兄
- ⑭ 飛騨と大和と廣瀬と龍田
- ⑮ 大津皇子と美濃トキミチツクリ
- ⑯ 死をまぬがれる聖泉
- ⑰ 謀反と飛騨千光寺と両面宿儺
- ⑱ 両面宿儺と飛騨の匠
・「坂口安吾:飛騨・高山の抹殺」記事一覧
※ 当記事は、上記シリーズ「⑨」です
以上、
「安吾の新日本地理:飛騨・高山の抹殺 ⑨」についてのブログ記事でした。