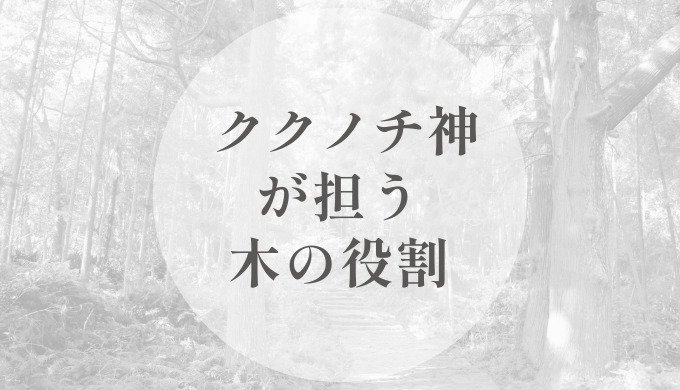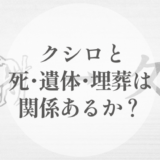久能智神は「木の神」と言われています。
木の神と聞くと、「植える」「育てる」「守る」といったイメージが、自然と浮かびます。
けれど、久能智神を調べていくと、どうもそのどれにも当てはまらない感覚が残ります。
破壊の神でも、再生の神でもない。
では、この神は、木のどの場面を引き受けていたのでしょうか。
この記事では、クシロに至る前段として、切られ、流され、使われる「木の工程」に立ち止まり、その配置を整理してみたいと思います。
木の神なのに、なぜ語りにくいのか

<久能智神に感じる違和感>
久能智神は、資料上では確かに「木の神」と説明されます。
けれど、その役割を説明しようとすると、言葉が途端に曖昧になります。
植林の神なのか、森を守る神なのか、あるいは自然崇拝の象徴なのか。
どれもそれらしく聞こえますが、決定打にはなりません。
実際、神話の中で久能智神が何かを「した」場面は、ほとんど語られていません。
山を拓いたわけでも、森を増やしたわけでもない。
破壊的な行為も、再生を導く奇跡も描かれない。
この沈黙こそが、違和感の正体ではないかと感じます。
もし久能智神が、植える神・守る神であれば、その働きはもっと分かりやすく語られていたはずです。
にもかかわらず、役割が掴みにくいまま残されている。
それは、この神が「目立つ場面」ではなく、語られにくい工程を引き受けていた可能性を示しているように思えます。
ここではまず、
「木の神なのに、何をしているのか分からない」
…というこの引っかかり自体を、問いとして置いておきたいと思います。
植える神でも、壊す神でもない

<スサノオ・五十猛との役割の違い>
木に関わる神としてよく知られている存在に、スサノオ や 五十猛 がいます。
スサノオは、場を壊し、秩序をひっくり返す神として語られます。
山や国を荒らし、結果として新しい局面を生む存在です。
その一方で、自身の体毛から樹木を生み出し、それを各地に植えたという伝承も残されています。
ただしその行為は、森を育てるというよりも、壊したあとの世界に「次の地形」を強制的に立ち上げるためのものとして描かれます。
そこには、明確な「転換点」があります。
一方、五十猛は、種をまき、土地に〈再び木が生える条件〉を残す神です。
人が再び住める土地になるかどうかを、時間に預ける役割を担います。
こちらもまた、働きが非常に分かりやすい神です。
五十猛の系譜をたどると、その子とされる 高倉下 の名が現れます。
ただ、この存在が「何をした人物なのか」は、実のところよく分かっていません。
紀国造の祖とされる一方で、紀国に強く祀られている形跡は薄く(※1)出雲口伝と記紀神話とで、その立ち位置は大きく揺れています。
 ぽの
ぽの
出雲側に近いようにも見え、一方で、記紀では神武を助ける側として描かれる。
どちらかにきれいに割り切れる存在とは言い切れません。
ここでは、高倉下を「役割の説明がつく存在」として扱うことはしません。
ただ、木を植える神の系譜の先に、こうした立場の定まらない名前が置かれていること自体が、この先の工程を考える上で、ひとつの引っかかりとして残ります。
では、久能智神はどこに置かれるのでしょうか。
スサノオのように、場を壊しながら木を生み出すわけでもなく、
五十猛のように、種をまき、次の時間を託すわけでもない。
この二者のあいだに、ぽっかりと空いた領域があります。
それは、切られたあと、まだ次が約束されていない時間。
森でもなく、資源でもなく、「まだ何者でもない木」が通過する工程です。
久能智神は、その曖昧で、しかし確実に存在する時間を引き受ける位置に置かれていたのではないか。
 ぽの
ぽの
(あくまでイメージです)
そう考えると、この神が多くを語られないまま残されていることにも、少しだけ理由が見えてくるように思えます。
切られ、流され、素材になる木

<久能智神が引き受ける「途中の工程」>
木は、切られた瞬間に役割を失うわけではありません。
むしろ、そこからが長い工程の始まりです。
山で切られ、川に落とされ、流され、乾かされ、運ばれる。
この間、木は神聖な存在でも、完成した資材でもありません。
川沿いを歩くと、今でも流木が溜まる場所があります。
それらは、自然物でありながら、そのまま朽ちていくものもあれば、状態次第では人の手に拾われ、使われることもある木です。
人が触れる可能性を含みつつ、まだ用途が決まっていない状態。
使われるか、捨てられるか、どちらにも転びうる、曖昧な位置にあります。
 ぽの
ぽの
久能智神が担っていたのは、まさにこの「宙づりの時間」ではないでしょうか。
切られたが、まだ意味を与えられていない木。
人の手に渡る直前の、危うい段階です。
この工程は、失敗すればただの廃材になります。
うまく扱われなければ、災害や事故にもつながる。
だからこそ、この段階を「誰かが引き受ける必要」があった。
久能智神は、木そのものではなく、木が通過する工程の神だった可能性が浮かび上がります。
クシロに至る前段としての「木」

<使う役割の手前にある、使われる工程>
クシロ(クシ)は、釧(腕輪)や 櫛といった「モノ」として知られています。
けれど本連載では、それを身につけ、扱う側の在り方にも目を向けています。
扱う者、使う者、境界を調整する側に立つ存在として。
同時に、その前に必ず存在するのが、「使われる側」の工程です。
釧や櫛、呪具に至る素材は、最初から神具として存在していたわけではありません。
木も、貝も、石も、一度は自然から切り離され、移動し、加工される。
この過程を飛ばして、いきなり人の役割を語ることはできません。
久能智神を、クシロの前段に置いて読むと、人が担う役割が急に浮き上がって見えます。
人が「扱う」以前に、世界の側で「扱われる工程」が整えられている。
久能智神は、人間社会に戻す前のワンクッションとして、木を受け取る場所だったのではないか。
そう考えると、クシロ連載 の中で、この神を挟む意味が見えてきます。
工程として置かれた神を、どう読むか

<結論を出さないための整理>
ここまで見てきたように、久能智神は「木の神」でありながら、木を支配する存在ではありません。
植えもせず、壊しもせず、再生も約束しない。
ただ、工程の途中に置かれている。
この読み方が正しいと断定することはできません。
ただ、そう置いてみると、語られなさや、役割の曖昧さが、無理なく繋がって見えてきます。
久能智神は、信仰の中心に立つ神ではなく、工程が滞らないための位置 に配置された存在。
目立たず、名乗らず、しかし欠けると困る。
そうした神のあり方として読むと、私の中では、この神の像が静かにつながってきます。
次は、この「工程」を人の側がどのように引き受けたのか。
その配置を、別の視点から見てみたいと思います。