クシロは、いつから「血族」として語られるようになったのでしょうか。
釧というモノや役割として見てきた流れの中で、系譜や氏族の名前として現れるクシロには、どこか説明しきれない違和感が残ります。
それは、血縁だったかどうかの問題というよりも、役割がどのような言語で語り直されてきたのか、という問いなのかもしれません。
この記事では、あえて「血族として読む」という視点に立ち、クシロが系譜へ回収されていく過程そのものを読んでいきます。
クシロは、いつから「血族」になったのか

クシロという語が、釧というモノや役割から離れ、氏族名や系譜として現れるとき、そこには一つの変化が起きているように感じます。
それは「役割を担う存在」から、「血によってつながる集団」への語り替えです。
久代氏(久々智氏)・櫛代族・櫛色族といった名称は、確かに血族や集団を示す言葉として理解されてきました。
しかし、それらが本当に同一の血縁集団だったのか、あるいは同時代に並立していたのかについては、はっきりしない部分も多く残っています。
 ぽの
ぽの
それは、最初から血族としてまとまっていたというより、後から「ひとまとまり」として説明される必要が生じた可能性を感じさせます。
ここではまず、クシロが「血族だったかどうか」を決めるのではなく、いつ・どの段階で血族という語り方が必要になったのかという視点に立ってみたいと思います。
役割は、そのままでは継承できない

これまで見てきたように、クシロを「役割」として読むと、その性質はとても流動的です。
場所に応じて形を変え、時代によって担い手が入れ替わり、必ずしも一箇所に固定されません。
けれど、役割というものは、そのままでは継承や管理が難しい側面もあります。
「誰が担うのか」「どこに責任があるのか」を明確にしなければ、制度や記録の中では扱いにくくなるからです。
実際、古代社会においては、祭祀や技術、境界管理のような役割が、特定の家や集団に割り当てられていく過程が各地で見られます。
実際に、役割として比べてみた記事はこちら。↓↓↓
 忌部・物部・中臣と「クシロ」|血族ではなく、役割として比べる
忌部・物部・中臣と「クシロ」|血族ではなく、役割として比べる
それは能力や適性の継承であると同時に、「この家が担うものだ」という理解を社会全体で共有するための工夫でもあったはずです。
役割が、役割のままでいられなくなったとき、別の言語が必要になる。
そのひとつが、「血族」という語り方だったのではないか。
ここから、クシロの語られ方をもう一段階、見直してみます。
血族という言語が、役割を固定する

血族という表現は、単に血のつながりを示すだけのものではありません。
それは、「この役割は、この系譜に属する」という理解を固定するための、分かりやすい翻訳でもあります。
実際の古代社会では、純粋な血縁だけでなく、養子や婚姻、擬制的な親子関係によって役割が継承されることも珍しくありませんでした。
それでも「血族」として語られることで、役割は安定し、外から見ても把握しやすくなります。
クシロもまた、そうした翻訳を受けた存在だった可能性があります。
本来は工程や機能として分散していたものが、「〇〇氏」「〇〇族」という形にまとめられることで、系譜の中に回収されていった。
私がいくつかの神社配置や土地の連なりを見ていて感じたのは、「ここが本拠」というよりも、「この役割を担っていた痕跡が残っている」という印象でした。
血族表現は、その痕跡を一本の線に結び直すための装置だったのかもしれません。
役割として読む視点と、血族として読む視点は対立しない

ここで注意したいのは、「役割として読む」視点と「血族として読む」視点を、対立させないことです。
どちらかが正しく、どちらかが誤りだと決める必要はありません。
前回までの記事では、クシロを血族と決めつけないために、あえて役割や配置から読んできました。
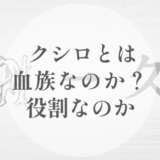 釧(クシロ)とは何か|血族ではなく「役割」として読む、その手前
釧(クシロ)とは何か|血族ではなく「役割」として読む、その手前
それは、血族という言語が生まれる前の層を見るためでした。
一方で、血族として語られるようになったこと自体も、歴史の一部です。
役割が固定され、管理され、記録されていく中で、血族という表現が選ばれた理由があったはずです。
読みのレイヤーを切り替えることで、同じ対象でも、見えてくるものが変わってきます。
その切り替え自体を「間違い」とせず、私は、どう語られてきたかを重ねて読んでいきたいと思っています。
クシロが血族に回収された、その先で

クシロが血族として語られるようになったとき、役割は安定した一方で、別の変化も起きた可能性があります。
それは、役割が特定の系譜に固定されることで、かえって見えにくくなる部分が生まれたことです。
役割が制度化され、系譜に回収されると、「誰が何をしていたのか」という具体的な工程は、語られにくくなっていきます。
名前は残るけれど、働きは抽象化される。
その結果、クシロという存在は、徐々に歴史の表舞台から姿を消していったのかもしれません。
この先では、そうした固定化の延長線上にある「消失」や「回収」のあり方について、もう少し視点を絞って考えてみたいと思います。
血族として語られたクシロの、その先に何が置かれたのか。
次は、そこに立ち止まってみる予定です。

