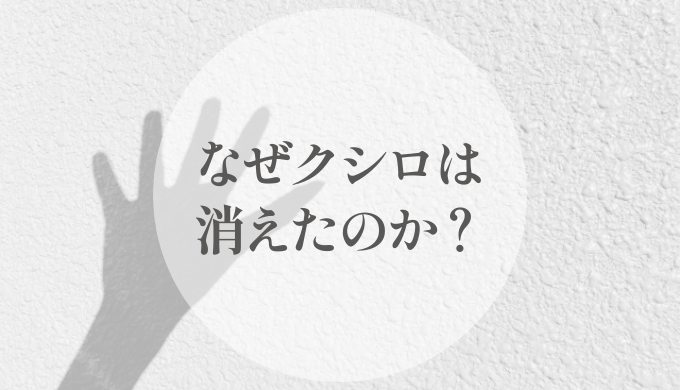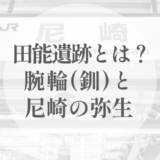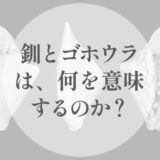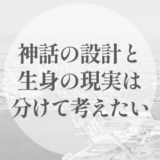釧(クシロ)は、ある時代を境に、考古学の表舞台から姿を消します。
そのため、しばしば「廃れた」「不要になった」と語られてきました。
けれど本当に、クシロは突然消えてしまったのでしょうか。
本記事では、勝敗や断絶としてではなく、役割の移動という視点から、クシロがどこへ回収されていったのかを、古墳という装置を手がかりに、考えてみたいと思います。
※ クシロという言葉や考え方については、
[関連記事:釧(クシロ)とは何か|血族ではなく『役割』として読む、その手前]
で、整理しています。
クシロは、本当に「消えた」のか

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した釧)
釧(クシロ)は、弥生後期の遺跡や生活空間では、はっきりとその姿を確認できます。
実際に 田能遺跡 で出土状況を見たときも、クシロは「特別な宝」ではなく、身体に近い位置で、日常と儀礼のあいだに置かれているように感じました。
ところが、古墳時代に入ると、状況は一変します。
古墳から釧はほとんど出土せず、「クシロを身につけた人」の像も見えなくなっていきます。
この変化は、しばしば「クシロ信仰の衰退」や「不要化」と説明されがちです。
しかし、本当にそう言い切ってよいのでしょうか。
消えたように見えるのは、物そのものなのか、それとも、私たちが注目している場所が変わっただけなのか。
この記事ではまず、「消えた」という言葉が生む違和感そのものから、考え直してみたいと思います。
クシロにあった三つのレイヤー

クシロを考えるとき、ひとつの見落としが起こりやすいと感じています。
それは、クシロを「釧というモノ」だけで捉えてしまうことです。
名称としての「クシロ」が残った場所については、
[関連記事:クシロがつく地名を、並べてみる]
で、別の角度から整理しています。
これまでの記事で触れてきたように、クシロには少なくとも、
モノとしての釧、
名称としての「クシロ」、
そして役割としての境界処理
…という、複数のレイヤーが重なっています。
田能遺跡で釧と管玉が並ぶ様子を見たときも、そこにあったのは単なる装身具以上の配置でした。

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した管玉)
身体の一部として境界を担う役割が、かたちを伴って可視化されていたように思えます。
重要なのは、これらのレイヤーが
同時に、同じかたちで消えるとは限らない
という点です。
モノが姿を消しても、役割だけが別の場所に移される、ということはあり得るのではないでしょうか。
古墳という装置が担ったもの

古墳に目を向けると、そこに集められているものの性質は、クシロとは大きく異なります。
鏡、玉、武器、埴輪。いずれも、権威や系譜、祖霊を「留める」ための装置として機能しているように見えます。
実際、古墳は一度築かれると、動かされることのない固定された場所です。
生と死のあいだを流動的に処理するというより、死を祖霊として社会の中心に据えるための構造物だと言えるでしょう。
現地で古墳群を歩いたとき、強く感じたのは「動かさないための力」でした。
囲い、積み上げ、記憶を集中させる。
その性質は、境界をまたぎ、固定しないクシロの役割とは、ほとんど反対側に位置しているように思えます。
クシロの役割は、どこへ回収されたのか

では、クシロの役割は古墳によって否定されたのでしょうか。
私は、そう単純ではないと感じています。
クシロが担っていたのは、死を流し、社会が壊れないように処理する役割でした。
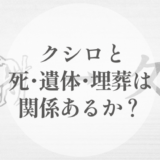 クシロと死・遺体・埋葬は、関係あるのか|身につけられた釧の、その後を考える
クシロと死・遺体・埋葬は、関係あるのか|身につけられた釧の、その後を考える
古墳時代になると、その役割そのものが不要になったというより、古墳という巨大な装置に一括してまとめ直されたように見えます。
個々の身体が担っていた境界管理が、制度と構造に回収されていった、と言い換えることもできるでしょう。
釧を身につけるという可視的な形は失われましたが、「死をどう扱うか」という問い自体が消えたわけではありません。
回収とは、排除ではなく、置き換えや統合に近い動きだった可能性があります。
古墳に「入らなかった」役割について

もうひとつ、見落としがちな点があります。
それは、クシロを担っていた人々が、古墳の主役にならなかった可能性です。
これは、敗北や卑賤を意味するものではありません。
むしろ、役割の設計が違っていた、と読む方が自然に思えます。
境界を処理し、流動性を保つクシロの役割は、「戻さない装置」である古墳には適さなかったのではないでしょうか。
ゴホウラのような、身につけて境界をまとう装置が、古墳に持ち込まれなかった理由も、そこに重なって見えてきます。
クシロは消えたのではなく、語られなくなり、見えなくなった。
その不可視化こそが、古墳時代への移行を考えるうえでの、ひとつの重要な手がかりなのかもしれません。