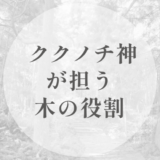忌部・物部・中臣は、よく「古代祭祀族」としてひとまとめに語られます。
けれど、クシロ(釧)に至るまでの工程を辿ってみると、それぞれが担っていた役割には、少しずつズレがあるようにも見えてきます。
彼らは本当に、同じ土俵で並ぶ存在だったのでしょうか。
この記事では、血縁や系譜から一度離れ、クシロを含めた「どの工程に置かれていた役割だったのか」という視点から、忌部・物部・中臣の位置関係を静かに整理していきます。
ここでいう「役割として読む」という視点については、以下の記事「釧(クシロ)とは何か|血族ではなく『役割』として読む、その手前」で整理しています。↓↓↓
[関連記事:釧(クシロ)とは何か|血族ではなく「役割」として読む、その手前]
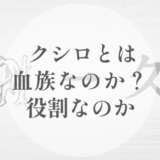 釧(クシロ)とは何か|血族ではなく「役割」として読む、その手前
釧(クシロ)とは何か|血族ではなく「役割」として読む、その手前
目次
忌部・中臣・物部は、なぜ並べて語られてきたのか

忌部・物部・中臣は、古代史の文脈では「王権を祭祀で支えた三氏族」として、ひとまとまりに語られることの多い存在です。
祭祀、武器や神宝の管理、祓い…それぞれの役割の違いには触れられていても、最終的には「ヤマト政権の中枢にいた一群」として、一括されがちです。
けれど、クシロという存在を手がかりに見直してみると、この並べ方そのものに、少し引っかかるものが残ります。
というのも、クシロが関わっていそうな工程は、「整える」「鎮める」「言葉にする」といった、祭祀として形を与えられた行為よりも、
その一歩手前
…触れるか、触れないかを判断する段階に、より近いように見えるからです。
もし三者が本当に同じ土俵に立っていたのなら、役割の説明は、もう少し整理されていてもよさそうです。
それでも曖昧さが残るのだとすれば、それは、もともと同列ではなく、異なる工程に置かれていた存在を、後から一つの枠に収めて語ってきた結果なのかもしれません。
「触れる役割」と「触れない役割」という分岐

クシロを追っていると、身につける物そのものよりも、「それをどう扱うか」が気になってきます。
つける・外す・渡す・置く…こうした工程は、物理的な行為でありながら、誰が触れてよいか/触れてはいけないかという境界の判断を含んでいます。
田能遺跡 で出土した腕輪も、最初は私にとって「おしゃれな装身具」に見えていました。
 ぽの
ぽの
ただ、出土状況や文脈を追ううちに、身につけること自体より、扱い方(触れ方、渡し方、置かれ方)に意味が偏っているような違和感が残るようになりました。
ここから見えてくるのは、穢れや死に “直接触れない” ために、役割そのものが分岐していく構造です。
釧と死・遺体・埋葬の距離感については、[関連記事:クシロと死・遺体・埋葬は、関係あるのか]で詳しく触れています。
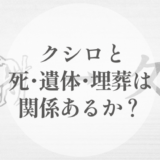 クシロと死・遺体・埋葬は、関係あるのか|身につけられた釧の、その後を考える
クシロと死・遺体・埋葬は、関係あるのか|身につけられた釧の、その後を考える
そして触れない側が、言葉や道具や媒介によって「触れないまま処理する」回路を持つ。
この回路を成立させる側に、忌部・物部・中臣が並んで見えてきます。
忌部・物部・中臣を「工程」で並べてみる

では、忌部・物部・中臣は「触れない処理」の中で、どこに置かれていたのでしょうか。
ここは断定せず、工程として並べます。

忌部・物部・中臣の共通点と相違点
忌部は、祭具・布・紙・媒介物など、「直接触れないための準備」を担う位置に見えます。
触れないことを成立させるために、境界の道具を整える。言葉が届く前段の『手続き』のような場所です。
物部は、神宝や武器など「物として保持されるもの」を管理する位置にいます。
ここでも重要なのは、暴力や権威ではなく、物質を『定位置に置く』ことで触れ方を制御する点です。
中臣は、祝詞や言葉によって事態を処理する位置にいます。
触れない代わりに、言語化して社会の側へ回収する。
穢れを『扱える形』に変換する役割です。
三者は、穢れに直接触れないための回路を、それぞれ別の方法で成立させていた…そう読むと並び方が安定します。
人が担う役割に目を向ける前に、自然物である「木」がどのように工程化されていくかについては、[関連記事:久久能智神が担う『木』の役割]で扱いました。
クシロが置かれた可能性のある、もう一つ手前の位置

では、クシロはどこに置かれていたのでしょうか。
忌部や物部、中臣の役割と重なる部分はありますが、完全に一致はしません。
クシロは、死を処理する役割そのものではなく、その直前…「これは扱ってよいのか」「誰が引き受けるのか」を判断する段階に関わっていた可能性があります。
出雲口伝では、死体そのものを強い穢れとして忌避したという記述が見られます。
もしそうだとすれば、死や穢れを「共同体の内側で処理しない」という選択が、かなり徹底していたことになります。
そうした思想圏が存在したことを踏まえると、クシロのような役割が、誰かに担われ、あるいは分離されていく必要性も、別の角度から見えてくる気がします。
身につける行為は、その判断が済んだ後の結果にすぎません。
ゴホウラ製の腕輪が南方由来であること、形が長く保持され続けたことも、即物的な実用より「工程の標識」としての性格を感じさせます。
クシロは、忌部・物部・中臣のいずれかに回収される前段階に置かれ、役割の分岐点として機能していた…そんな配置が浮かび上がります。
役割が、なぜ「血族」や「氏族」として語られるようになったのか

こうして工程で見ていくと、忌部・物部・中臣、そしてクシロは、もともと連続したプロセスの中に配置されていたように見えます。
ところが、それが後世になるにつれ、「誰の家か」「どの氏族か」という形で固定されていきました。
こうした「役割が血縁へと置き換えられていく過程」は、記紀神話全体の編集方針とも重なります。
詳しくは[関連記事:記紀神話に残された矛盾を読む]で整理しています。
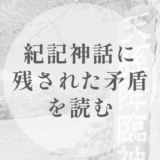 記紀神話に残された矛盾を読む|設計として書かれたことと、書かれなかったこと
記紀神話に残された矛盾を読む|設計として書かれたことと、書かれなかったこと
役割は本来、状況に応じて動くものです。
しかし制度や記録の中では、流動性は扱いにくく、血縁や家名に結びつけた方が管理しやすかったのかもしれません。
その結果、工程の違いは系譜の違いへと置き換えられていきます。
この変換そのものが善悪や勝敗を意味するわけではありません。
ただ、クシロを含む役割の配置を読み直すことで、「語られ方が変わった瞬間」が見えてくる気がしています。