兵庫県尼崎市~伊丹市にかけて存在する 田能遺跡 をご存じですか?
目次
尼崎・伊丹にある「田能遺跡」って?
12月20日をもちまして開館50周年記念特別展「田能遺跡の弥生人―田能家の人々―」を閉会しました❗️🎉🥳会期中の総入館者数は5795人でした✨👪👨👩👧👦👩👧👦お子様から人生の大先輩まで多くの方々にご来館いただき、たくさんの笑顔と感謝をいただけたこと大変うれしく思います😊💖#田能資料館 #田能遺跡 pic.twitter.com/FVnpvSqsDw
— 田能資料館 (@tanosiryokan) December 22, 2020
尼っ子(尼崎の子ども達)は、小学生の頃に 社会見学 やら 遠足 で必ず訪れるので、みんな 知ってるのですけれども。
全国的に見ると全然有名じゃないっぽい…?!
でもでも、とっても スゴイ遺跡 なのです。
超美しい「碧玉製管玉(ヘキギョクセイクダマ)」などが出土していて、とてもロマンあふれる遺跡なのです。
\ 実物(一部)見れます /
参考 尼崎市立田能資料館文化遺産オンライン 参考 尼崎の指定文化財:田能遺跡出土の遺物尼崎市発見当時は『日本のツタンカーメン』なんて騒がれて、かなりのニュースになったのですよ。
田能遺跡は弥生時代の遺跡
「田能遺跡」は 弥生時代 の遺跡です。
弥生時代 とは?紀元前10世紀頃 ~ 紀元後2世紀末頃 までを指します。
すなわち、約 3000年前~1700年前頃 の遺跡ということですね。
(↑2023年時点でのおよそ計算…合ってますかね…?)
発見のきっかけ(1965年)
発見されたのは、1965年(昭和40年)。
尼崎・伊丹・西宮三市共同による 工業用水園田配水場の建設工事中に「大量の弥生土器」が発見されたことがきっかけでした。
そして、この場所に「大規模な 弥生時代の遺跡」があることが判明し、調査が開始されました。
・
・
調査の結果、遺跡 は 弥生時代全期間 にわたる集落跡であると判明。
東西110m、南北120mの範囲内に拡がり、住居跡・土坑・溝・柱穴のほか 無数の小さな穴 が発掘されました。
さらに 木棺墓・木蓋土坑墓・土坑墓・壷棺墓・甕棺墓 などの 墓が17基 発見され、それまで不明であった 弥生時代近畿地方の墓制 を明らかにする手がかりとなりました。
・
・
当初は調査後、計画通りに「配水場建設」を進めて 遺跡を破壊 する予定だったらしいのです。(マジか!)
しかし、保存運動が高まり、その結果、遺跡の重要な部分を保存することが 無事決定したとのこと。(良かった…)
そして、めでたく 1969年(昭和44年)6月30日に 国の史跡に指定 される運びとなりました。(メデタシ・メデタシ)
何が出土した?
特に注目されたのが、木棺の発見でした。
木は腐りやすいため、それまでは推測でしかなかった 弥生時代の 木棺埋葬の風習 が、初めて具体的な形で証明された ということです。
第1次調査では、木棺墓 から 人骨も発見 されたのだとか!
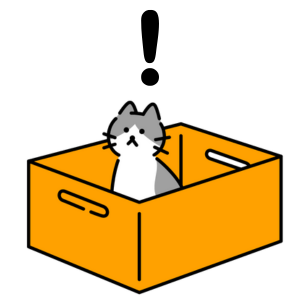
そして一番の驚きは、そのお墓に「丁寧に埋葬された被葬者」の姿だったでした。
丁寧に埋葬された被葬者
発見されたお墓は 17基。
そのうち、第16号墓 の被葬者(男性)は なんと!!
632個以上の 碧玉製管玉 が胸部付近に ある状態で発見されたのでした。
そして、さらに 第17号墓 では 左腕に白銅製の腕輪 を身に着けた状態 の男性が発見されたのでした 。
丁寧に作られた墓 に埋葬されていたことなどと併せ、この 2基の墓の被葬者が 特別な扱いを受けていたこと が分かります。
出土品の一部はネットで見れます
第1次調査で発見された「木棺墓」や「人骨」の他、土器多数・石斧などの石器・木製品・骨類・鉄製品なども発見されています。
そして、以下の三点は 兵庫県指定文化財に指定されました。
これら、三点を含めた出土品の一部は「文化遺産オンライン」で見ることができます。↓↓↓
参考 田能遺跡資料館文化遺産オンライン※「釧(クシロ)って何だ?農耕具か何かか?」と思って調べたら、なんと「古代の腕輪」とのこと。
なにそれ?!腕輪 とか!!超ステキ!
最初に、「碧玉製管玉」を見て、ビックリ&感動だったのですが、腕輪 まであったとは。
それにしても、腕輪 とか 碧玉とか!
玉ですよ?タマ!ギョク!
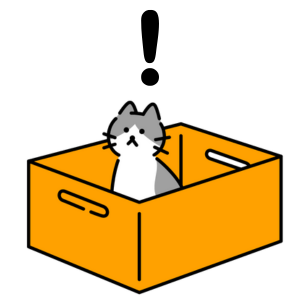
弥生時代の 尼崎市(アマ)にいた、「偉い人」や「祭祀を行う人」が身に着けていたのだろうか?…とか。
「玉を作る技術者集団」がいたのだろうか?…とか。
いろんな 想像が膨らんでワクワクしますね。
<碧玉製管玉:詳細>
・鮮明な画像はこちら(碧玉製管玉)

碧玉製管玉を胸に着けていた 被葬者は「老年とみられる男性」とのこと。
第17号墓に接して埋葬された第16号墓の被葬者(男性)の胸部付近から発見された 632個におよぶ 碧玉製の管玉。
大きさには大小があり、長さ0.72から2.33cm、太さ0.33から0.6cmのものがあります。
長さで最も多いのは1.48cm、太さで最も多いのは0.49cmのものです。
近畿地方では最大量の出土例です。廃土中に発見されたため一部が廃棄された可能性があり、当初は数量的に もう少し多い数の管玉が首飾りに使用されていた ものと思われます。
地点を異にして 碧玉の原石 が2点 検出されています。
その内の1点には 分割のための溝が彫りこまれており 田能遺跡において管玉の製作が行われていたこと を想定させます。
(引用:尼崎市)
「碧玉製の管玉」に関しては、尼っ子リンリン 様 のサイトがとても参考になります。↓↓↓
\ 田能遺跡レポートがすばらしいです /
・ブラガサキ:なぜ田能遺跡は今も残っているのか(後編):尼っ子リンリン
この「碧玉製管玉」については、「尼っ子リンリン 様」のサイトではこのように書かれていました。↓↓↓
- 色が鮮やかなものは大陸からの 輸入品
- くすんだ抜け感のある色のものは 石川県産
輸入品 ということにも驚かされますが、
石川県産!!にも 驚きです。
![]() ぽの
ぽの
そして、出雲の大国主 と結婚した越国の「沼河比売(高志沼河姫)」のお話も有名です。
しかし、正直「イヤイヤイヤ、出雲(島根) と 越国(石川県周辺エリア)とか遠すぎやろう?!そんなん、出会う?!
…とか、思ったりしたこともあったのですが。
あり得るのですね~。スゴイなぁ。古代…。
ちなみに、私も 子どもの頃に これらの実物を見たはずなのですけれども「どこ産の玉か?」とか全く興味持って聞いてなかったことが悔やまれますね…。(大人になった今、再訪したすぎます。)
<白銅製釧:詳細>
・鮮明な画像はこちら(白銅製釧)

遺跡の南西の端に埋葬された第17号墓の被葬者(男性)が左腕に着装した状態で発見された腕輪。
・外径は縦7.10cm、横5.58cm、内径は縦6.15cm、横4.7cm、環の幅は0.75cm、厚さ0.5cmあります。
・「D」字状の不整五角形をなし、外面はよく研磨されていますが、内面には鋳型の合わせ目が部分的に残っています。
・その形から 南海産の大型の巻貝「ゴホウラ」を縦に切断して作られた貝製の腕輪を比較的忠実に模して製作されたと考えられます。
・近畿地方の弥生時代の被葬者の検出例としては装身具を着装した数少ない例の一つです。
・(引用:尼崎市)
「釧(クシロ)=腕輪」に関しても、尼っ子リンリン 様 のサイトがとても参考になります。↓↓↓
\ 田能遺跡レポートがすばらしいです /
・ブラガサキ:なぜ田能遺跡は今も残っているのか(後編):尼っ子リンリン
この「白銅製釧」について、「尼っ子リンリン 様」のサイトに めちゃくちゃ面白い(興味深い)ことが書かれていました。↓↓↓
- 腕輪の形がいびつなのは、ゆがんだのではなく「もともとこんないびつな形」
- 「ゴホウラ(貝)の腕輪」を銅で(わざわざ)造っている(ゴホウラは南方の貝でこの辺には生息してないから しゃーなしで?)
- 「貝の欠けた箇所」も(なぜか)忠実に再現して腕輪にしている
- 九州では「貝製の腕輪に加工してつけることで呪力を得られる」との考えがあった
これを読んで「ゴホウラの腕輪」(銅製ではなく、本物のゴホウラでできた腕輪)が気になりすぎて調べてみると、こんな話がヒットしました。
↓↓↓
▼ ゴホウラに腕輪について書いてくださっています(KUMA0504 様)
・再出発日記:腕輪をした英雄の死をめぐるミステリー 夏旅6-3(山口):KUMA0504
「土井ヶ浜ミュージアム」で出土した「大人の腕についた状態で発見された『ゴホウラの腕輪』」はとても小さいそう。
いくら小柄な大人でも腕を通す事は難しいのだとか。
<補足>
土井ヶ浜遺跡:山口県下関市豊北町大字神田上891−8(地図)
その件に関してこのように書かれていました。↓↓↓
(~前略~)
・「ゴホウラの腕輪は、ほとんどは墓の副葬品として出てくるのです。
・もし腕輪をして出土してきたとしたならば、それは小さい頃からしていたということです。
・だから、この人骨は「戦士」ではない。激しい運動は出来ません。
・ずっと高貴な人でした。
・しかし、なぜか頭を潰され、無数の矢を打ち込まれて葬られている。」
・「何故か。一つ考えられるのは、生前大きな失敗をしてその罰でこのような葬られ方をしたのか。
・あるいは、なにかの儀式で、忌みを遠ざけるためにこのように葬られたのか。」
・(~後略~)
・(引用:KUMA0504 様)
↑↑↑
ゴホウラの腕輪 を付けたこの被葬者は、発掘後「戦士」「英雄」と呼ばれ、その墓は「戦士の墓」あるいは「英雄の墓」という名称になっている。
しかし、(大人が腕を通すには「小さすぎる ゴウホラの腕輪」を子どもの頃からしているその人は)「戦士ではない」。
…という話、「真実はいったいどういう事なのか?」とても気になる話ですね。
<Wikipedia>
・土井ヶ浜遺跡
<銅剣鋳型:詳細>
・鮮明な画像はこちら(銅剣鋳型)
昭和40年に行われた 田能遺跡の 発掘調査の際、第4調査区 南端の 不整形な土坑中から、弥生時代 中期前半の 土器の破片 と一緒に発見されました。
・砂岩製。剣を彫りこんだ面は 現状を保つと考えられてきましたが、掘りこみが浅すぎることから、二次的な研ぎを受けていると考えた方がよいようです。
・側面には 砥石として使用された痕跡が 残されています。
・現存長6.6cm、最大幅6.6cm、最大厚み5.3cm の直方体の一面に 銅剣の茎(なかご)部分と 関(まち)から上がわずかに残されている 銅剣の鋳型 です。
・彫りこまれている 剣の現存寸法は、全長5.8cm、剣身部長3.6cm、剣身部最大幅4.7cm、関幅4.4cm、脊幅1.7cm、茎部長2.4cm、同幅1.65cmである。
・この鋳型から復元される銅剣は 岩永省三氏の編年による 中細銅剣a類に属すると考えられています。
・この鋳型の発見によって 近畿地方でも銅剣を製作していたこと が明らかになりました。
・(引用:尼崎市)
田能遺跡では「銅剣」や「銅矛」は出土していない。(そのはず…)
でも、「銅剣鋳型」が出土したということは、ここで「銅剣」を作ってたんだね。
(まさか、「鋳型」だけ作ってた…とか無いだろうし?
>この鋳型の発見によって 近畿地方でも銅剣を製作していたこと が明らかになりました
…って、書いてありますもんね。↑↑↑
・
・
【余談】
これは、田能遺跡 の話ではありませんが…↓↓↓
「銅矛」といえば、「尼崎(アマガサキ)」と似た響きを持つ 高知の「天崎遺跡(アマサキ)」から出土している「銅矛」がものすごく立派ですね。
#仁淀川水系 #高知県 #手箱山・浦島伝説
天崎遺跡出土「中広形銅矛(4本)」 pic.twitter.com/GPLc0JjzjZ— しろくま君古紙回収事業部 (@kochishigyo1) February 17, 2021
※再埋納時期が「鎌倉時代」っていうのはよくわかりませんが…
「中広形銅矛(天崎遺跡)」
再埋納時期は・・・・なんと鎌倉時代(謎) pic.twitter.com/AUuyH44BHT
— しろくま君古紙回収事業部 (@kochishigyo1) April 15, 2021
ちなみに、「鉄器」が使用されるようになったのは弥生時代で、「青銅器」の伝来とほぼ同じ時期です。
主に「鉄器」は 実用品 として、「青銅器」は 祭祀道具として使用されていたとのことです。
参考サイト
<公式>
・田能遺跡:X(エックス)
・【YouTube】映画「田能遺跡」(動画)
・【YouTube】弥生時代の町-田能遺跡発掘調査レポート-(動画)
・【YouTube】弥生からの贈り物(動画)
<参考サイト>
・尼崎市:田能遺跡出土の遺物について
・尼崎市:田能資料館
・文化遺跡オンライン:田能遺跡
・全国子ども考古学教室:田能遺跡
・地図情報尼崎:遺跡分布図
・地図情報尼崎:史跡分布図
<Wikipedia>
・田能遺跡
▼ 田能遺跡の詳細でわかりやすいレポートです(尼っ子リンリン 様)
・ブラガサキ:なぜ田能遺跡は今も残っているのか(前編):尼っ子リンリン
・ブラガサキ:なぜ田能遺跡は今も残っているのか(後編):尼っ子リンリン
▼ 田能遺跡で出土した「勾玉」の写真を載せて下さっています(アキラ墳 様)
・人気スポット?(社寺&花)のブログ:弥生時代を覗いて見ましょう:アキラ墳
▼ ゴホウラに腕輪について書いてくださっています(KUMA0504 様)
・再出発日記:腕輪をした英雄の死をめぐるミステリー 夏旅6-3(山口):KUMA0504
▼ 田能は物部氏の本拠地?!
・Tomのスペース:記紀の物部氏の説話は本当か
尼崎・伊丹にある「田能遺跡」って?|まとめ
住所:兵庫県尼崎市田能6丁目5−1
というわけで、
尼崎・伊丹にある「田能遺跡」は、古代のアクセサリーが出てくるなど、めちゃくちゃロマンあふれる遺跡なのでした。
以上、
尼崎・伊丹にある「田能遺跡」って?…について のブログ記事でした。


