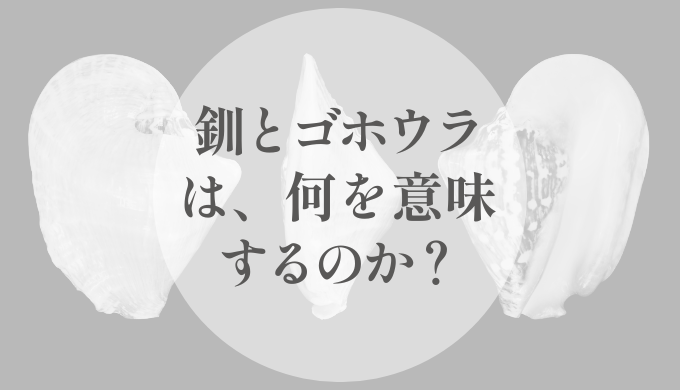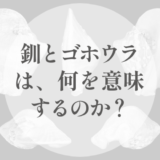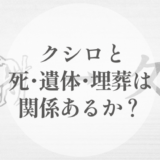前回の記事
[釧(腕輪)とゴホウラは、何を意味するのか|身につける形と素材から読む、クシロの役割]では、
釧(クシロ)を 腕に身につける形、そして 素材としての貝 に注目し、それが単なる装飾や権威表示ではない可能性について考えてきました。
その過程で、とくに引っかかりとして残ったのが、数ある素材の中で、なぜ繰り返し ゴホウラ が選ばれてきたのか、という点です。
ゴホウラは、日本列島では(本州以北の内陸では)自然に手に入る貝ではありません。
南方の海に由来し、内陸に持ち込まれることで初めて存在する素材です。
そのため、「交易品」「貴重品」「特別な素材」と説明されることも多くあります。
けれど、もし重要なのが「希少であること」だけであれば、同じ条件を満たす素材は他にもあったはずです。
それでもゴホウラが選ばれ、しかも 腕に装着される釧 という形で使われ続けたことには、素材そのものが持つ性質…とくに 境界との関わり方 が深く関係しているように思えます。
この回では、クシロという言葉や系譜から一度距離を取り、ゴホウラという「貝」そのもの に視点を寄せてみたいと思います。
ゴホウラは「どこから来た貝」なのか

<南方・非日常・持ち込まれる素材>
ゴホウラは、温暖な南方の海域に生息する大型の巻貝です。
日本列島、とくに本州以北の内陸部では、自然環境の中で出会うことはありません。
つまりゴホウラは、「そこに元からあった素材」ではなく、どこか別の場所から、意図的に運ばれてきた素材 です。
この「来歴」は、とても重要です。
土や石のように、足元にいくらでもあるものでもなく、動植物のように、その土地で育つものでもない。
- ゴホウラは、海の向こうから来る
- 日常生活の延長では手に入らない
- それ自体が移動の痕跡を帯びている
そんな素材です。
この時点で、ゴホウラはすでに「境界を越えてきたもの」と言えます。
海と陸。
向こう側とこちら側。
日常と非日常。
ゴホウラは、それらの境目を通過した結果として、人の手元に現れる貝なのです。
交易品である、という説明は間違ってはいません。
けれど重要なのは、交易によって【運ばれてきた】という事実そのもの です。
ゴホウラは、境界を越える工程を経て、初めて使われる素材でした。
この性質は、後に釧として腕に装着されるとき、別の形で再び現れてくることになります。
貝という存在の特殊性

ゴホウラに限らず、そもそも「貝」という存在そのものが、かなり特殊です。
貝は生き物ですが、その身体は やわらかな中身 と、硬い殻 にはっきりと分かれています。
生きているあいだ、殻は中身を包み、守る「器」として機能します。
けれど、いったん中身が失われると、殻だけが残り、まるで最初から「空の器」であったかのように存在し続けます。
つまり貝は、生きているあいだは「内を守るもの」であり、死後は「中身のない形」として残るもの…そうした二重の性質を持っています。
骨のように、死そのものを直接的に想起させる素材でもなく、石や金属のように、最初から無機質な素材でもありません。
貝はその中間にあります。
生き物でありながら、中身が不在になっても、形だけが残る。
この性質は、生と死、内と外、在と不在…といった境界を扱う文脈と、とても相性がよいように思えます。
実際、貝殻は世界各地で、墓や副葬品・儀礼具、そして魔除けや護符 として用いられてきました。
そこでは、貝が「美しいから」だけで選ばれているとは考えにくく、中身が抜けても役割を失わない形 という点が、重視されていた可能性があります。
貝殻は、「何かが通過したあと」を示す痕跡でもあります。
かつてそこに生命があったこと、そして、今はもうそこにいないこと。
その両方を同時に含んだ状態で、貝殻は存在し続けます。
ゴホウラもまた、そうした「貝」という存在の特性を、はっきりと備えた素材です。
そしてゴホウラの場合、この性質は 形そのもの によって、さらに強調されることになります。
ゴホウラの形が示すもの

ゴホウラを特徴づけているのは、その大きさや希少性だけではありません。
むしろ目を引くのは、殻が描く独特の「巻き」のかたちです。
ゴホウラの殻は、単純な円や直線ではなく、内側へ、内側へと巻き込みながら形をつくっています。
外から内へ。開いているようで、どこか閉じていく構造。
この「巻き」は、見る角度によっては、鉤(かぎ)のような形にも見えます。
直線的に進もうとするものを、そのまま通さず、途中で引っかけ、留めるような形です。
【補足】
なお、貝輪(銅釧)についての研究では、初期段階では貝本来の螺旋構造を保ち、鉤状突起が目立たない形が多い一方、後期になるにつれて螺旋構造を簡略化し、ゴホウラ特有の鉤状突起を強調する方向へ変化していくことが指摘されています。
その結果、立岩型は「有鉤釧」として分類されるようになります。
田能遺跡の釧は、初期の立岩型に近い形を持ちながらも「無鉤」に分類されています。
この点は、単なる発達段階の違いというより、「鉤を強調する方向とは異なる選択」が行われていた可能性を示しているようにも見えます。
[参考:iMuseum|貝輪の変遷と鉤の強調 ]
これは、装飾として考えると、やや不思議な形でもあります。
完全な円でもなく、左右対称でもない。
美しさだけを目的とするなら、もっと分かりやすい形が選ばれてもよさそうです。
 ぽの
ぽの
でも、この「歪んだ形」にこそ意味があるかも…?と。
それでも、この「巻き」を持つ形が、繰り返し腕輪として模倣されてきました。
実際、田能遺跡から出土した白銅製の釧も、自然な円ではなく、巻貝を思わせる歪みを残しています。

(引用:尼崎市|田能遺跡から出土した釧)
素材が金属に置き換えられても、形そのものは捨てられていない。
この点は、ゴホウラの「形」が、単なる見た目以上の意味を持っていたことを示唆します。
巻く、という動きは、閉じる・囲う・内へ引き寄せる 動きでもあります。
同時にそれは、外へ抜けていくものを、そのままにはしないという性質を持ちます。
ゴホウラの形は、何かを外に向かって放出するというより、境界の途中で留めるような構造をしています。
この「留める」「引き止める」感覚は、後に見るように、貝が魔除けとして用いられる文脈とも重なっていきます。
ゴホウラの形は、意味を描いた記号というよりも、働きを内包した構造に近いのかもしれません。
貝の中に何かを納める。
あるいは、通過しようとするものを、途中で受け止める。
そうした性質が、この巻いた形そのものに、静かに埋め込まれているように見えるのです。
魔除けとしての貝との連続性

ゴホウラの形が持つ「巻く」「留める」「引き止める」といった性質は、日本列島各地に残る 貝の使われ方 とも、ゆるやかにつながっています。
たとえば沖縄では、スジガイなどの貝殻が、魔除けや護符として用いられてきました。
それらは、必ずしも華美な装飾として扱われるわけではなく、身につけられたり、家の入口に置かれたりと、境界に近い場所で使われることが多い素材です。
ここで重要なのは、「悪いもの」をどう定義するか、という点ではありません。
多くの民俗的文脈において、避けられる対象は、
- まっすぐ入り込んでくるもの
- 境界を無視して通過するもの
- 内と外の区別を乱すもの
として捉えられてきました。
そのため、魔除けに用いられる素材には、通過を妨げる形や、引っかかりを生む構造が選ばれる傾向があります。
牙や爪が用いられるのも、その一例です。
鋭く、曲がり、直線的に進むものを遮る。
貝殻もまた、この系譜に位置づけることができます。
とくに巻貝は、内部へと巻き込みながら、簡単には通り抜けられない構造をしています。
ゴホウラの殻が持つ 巻きと鉤のような形は、こうした魔除け的な感覚と、強く重なり合います。
ここで言いたいのは、ゴホウラ製の釧が「魔除けそのもの」だった、と断定することではありません。
 ぽの
ぽの
むしろ、
- 魔を祓う
- 悪を撃退する
といった分かりやすい機能以前に、
境界を乱させない
通過をそのままにしない
という、より基本的な感覚が共有されていたのではないか、という点です。
ゴホウラの形は、何かを排除するためというより、境界の途中で受け止めるための形に見えます。
それは、内と外を完全に切り分けるのでもなく、無防備に開いてしまうのでもない。
境界を「保つ」ための、穏やかな制御に近いものです。
こうして見ると、ゴホウラが釧という形で身につけられたことも、単なる装飾や呪術という枠を越えて、境界に関わる行為や状態を、身体にまとわせる ための選択だった可能性が、少しずつ浮かび上がってきます。
なぜ「腕」に置かれたのか

ゴホウラの性質を、「境界を越えてきた素材」「内と外を分ける殻」「通過を留める形」として見てきました。
では、それがなぜ 腕 に置かれたのでしょうか。
腕は、身体の中でも少し特別な部位です。
頭や胴のように 人格や身分を象徴する中心ではなく、足のように常に地面に接している部位でもありません。
腕は、内側に属しながら、最も早く外へ出る場所です。
何かを渡すとき。
何かに触れるとき。
境界を越えて行為を始めるとき。
多くの場合、まず外に出るのは腕です。
この性質は、釧が腕輪として用いられた理由を考える上で、とても重要に思えます。
もし釧が、身分や権威を示すための装飾であったなら、首や胸といった、より視線を集める場所に置かれても不思議ではありません。
それでも釧は、一貫して腕に置かれています。
これは、「見せる」ためというより、行為とともに在ることが、前提とされていた配置のように見えます。
ゴホウラ製の釧は、腕という境界部位に置かれることで、
- 内と外
- 人と環境
- 生と、その外側
そうした境目に立つ行為そのものに、境界をまとう条件を与えていたのかもしれません。
身につける、という行為は、ただ所有することとは違います。
それは、身体の動きと切り離せなくなり、外すまでのあいだ、常にその条件を引き受け続けることでもあります。
ゴホウラの釧は、誰であるかを示す標識というより、
今、その人が どの境界に関わっているのか
を示すための、一時的な装置だった可能性があります。
そう考えると、ゴホウラという素材が持つ性質と、腕という部位の選択は、偶然の組み合わせではなく、
境界を扱うための配置として、互いに深く呼応していたように見えてきます。